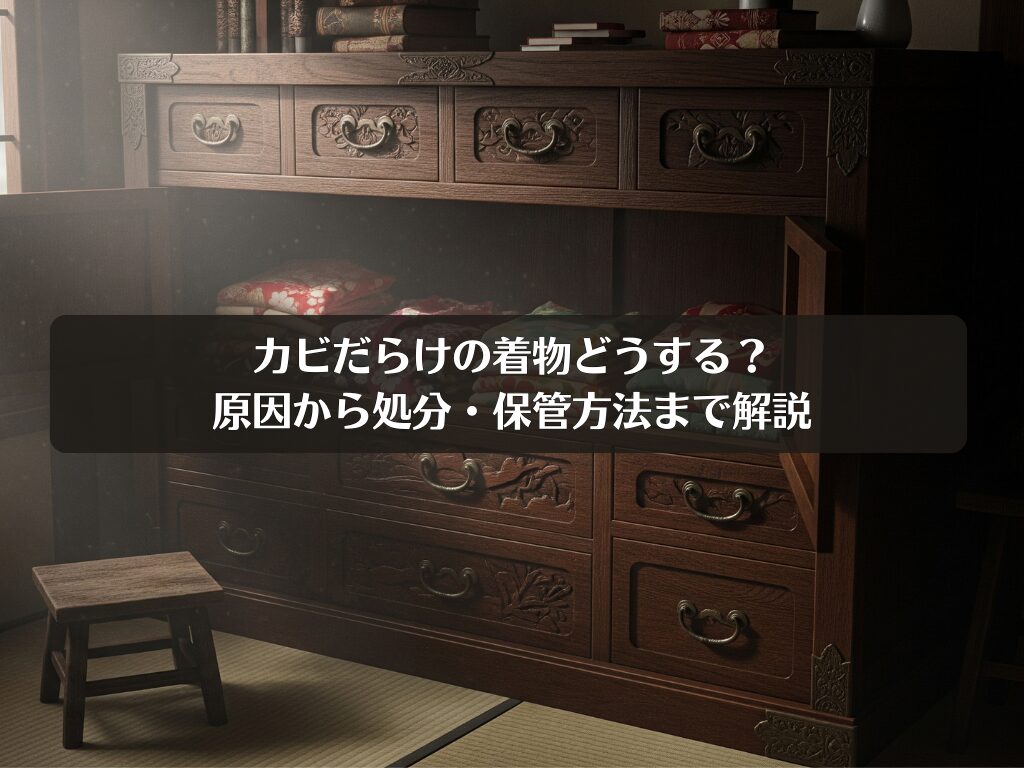タンスの奥から久しぶりに取り出した着物が、カビだらけになっていて愕然とした経験はありませんか。特に大切な喪服であったり、広範囲に茶色いシミが浮き出ていたりすると、どう対処すべきか途方に暮れてしまいますよね。
このカビの本当の原因はなぜなのか、自分でできる安全な取り方や落とし方はあるのか、あるいは「ベンジンなどを使っても大丈夫なのか?」といった疑問が次々と浮かぶことでしょう。
また、カビの見分け方や、着物の素材によって手入れ法が違うのか、そして何より「他の着物にうつりますか?」など不安は尽きません。
専門業者に依頼する場合のクリーニング料金や、状態によっては高額になると聞く全体の料金、さらには処分・捨てる以外の選択肢としてリメイクやリサイクルは可能なのか、知りたいことは多岐にわたるはずです。
この記事では、カビだらけの着物に直面した際のあらゆる疑問に答えるべく、適切な保管方法や日頃の注意点に至るまで、網羅的に情報をまとめました。
失敗や後悔を避けるため、業者・専門店に相談すべきケースも含めて詳しく解説していきます。
カビだらけの着物になるのはなぜ?原因と対処法
タンスの中で静かに広がるカビは、見た目の問題だけでなく、着物そのものを傷める深刻な事態です。このセクションでは、なぜ着物にカビが発生するのかという根本的な原因から、ご自身でできる初期対応、そしてその限界と注意点について詳しく解説します。
素材と湿気が原因?なぜカビが生えるのか
着物にカビが発生してしまう背景には、日本の気候と着物ならではの素材特性が深く関わっています。
カビが繁殖するためには「湿度」「温度」「栄養」「酸素」の4つの条件が必要ですが、着物の保管環境はこれらの条件を満たしやすい傾向にあります。
カビが好む環境とは
一般的にカビは、湿度が60%を超え、気温が5℃から35℃程度の環境で活動を始めます。
特に湿度が75%以上になると繁殖スピードが格段に上がると言われており、高温多湿な日本の梅雨時から夏にかけては、まさにカビにとって絶好の季節なのです。
締め切ったタンスや押し入れの中は空気が滞留しやすく、湿気がこもりやすいため、カビの温床となり得ます。
着物特有のカビ発生要因
さらに、着物自体がカビの「栄養」となりやすい特性を持っています。
第一に、多くの着物に使われる正絹(シルク)は、その約7割がタンパク質で構成されています。このタンパク質が、カビにとって格好の栄養源となってしまうのです。
第二に、着用時に付着した汗や皮脂、食べこぼしなどの目に見えない汚れも、カビの繁殖を助ける原因となります。
そして第三に、着物の染色工程で用いられる「地糊(じのり)」の存在が挙げられます。
この糊には湿気を吸収しやすい性質があるため、空気中の水分を着物が取り込み、内部に湿気を溜め込む一因となっているのです。
これらの要因が複合的に絡み合うことで、大切に保管しているはずの着物に、いつの間にかカビが発生してしまうという事態が引き起こされます。

白や茶色などカビの色の見分け方
着物に発生したカビは、その色によって進行度や危険性をある程度判断することができます。
カビは時間を経るごとに色が変化し、深刻度を増していくため、早期発見と色の見極めが対処の鍵を握ります。
白カビ:初期段階のサイン
白く点々とした斑点や、綿ぼこりのように見えるものは「白カビ」です。これはカビの発生初期段階であり、多くは生地の表面に付着しています。
この段階で発見できれば、比較的ダメージは浅く、適切な処置で除去できる可能性が高いです。しかし、白カビは胞子を飛散させやすいため、取り扱いには注意が必要です。
また、淡い色の着物の場合、白カビは発見が遅れがちになるため、定期的な点検が欠かせません。
黄カビ(黄変):要注意の変色段階
白カビを放置したり、汗の成分が酸化したりすると、黄色やオレンジ、茶色がかったシミのような「黄カビ」に変化します。
これは「黄変(おうへん)」とも呼ばれ、カビの菌糸が繊維の奥深くまで侵食し、生地自体が化学変化を起こしている状態です。
この段階になると、表面を払うだけでは落とすことができず、ご家庭での完全な除去は極めて困難になります。専門業者による特殊な漂白やシミ抜きが必要となるケースがほとんどです。
黒カビ・こげ茶カビ:最も深刻な末期症状
カビがさらに進行し、発生から10年以上経過すると、黒やこげ茶色の点々としたカビが発生します。
これは最も深刻な状態で、カビが繊維組織を分解し、生地そのものを著しく劣化させている可能性が高いです。
この段階に至ると、専門家が最善を尽くしても完全に元通りにすることは非常に難しく、クリーニング作業中に生地が破れてしまうリスクさえ伴います。
黒カビを発見した場合は、修復が困難であることを覚悟の上で、専門家に相談する必要があります。
以上の点を踏まえると、カビは色によって進行度が異なり、白いうちに発見し、迅速に対処することが着物を守る上で極めて大切であると言えます。
カビ対策についてもっと詳しく知りたい方は、専門サイトの〈カビQ&A〉ページをご覧ください。具体的なカビ情報が詳しくまとめられています。
衛生微生物研究センター:カビQ&A|よくある質問と対処法

「他の着物にうつりますか?」という疑問
カビの生えた着物を見つけた際に、最も懸念されることの一つが「他の衣類への影響」です。この疑問に対する答えは、残念ながら「はい、うつります」となります。
カビは菌類の一種であり、目に見えないほどの小さな「胞子」を空気中に放出することで繁殖します。
カビが生えた着物をタンスやクローゼットにそのまま放置しておくと、放出された胞子が空気の流れに乗って飛散し、近くにある他の着物や衣類に付着してしまうのです。
付着した胞子は、そこがカビの繁殖に適した環境(適度な湿度や温度)であれば、新たに根を張り、菌糸を伸ばして成長を始めます。
つまり、一つの着物に発生したカビが、タンス全体の汚染源となりかねないということです。
したがって、カビの生えた着物を発見した場合は、二次被害を防ぐために、直ちに以下の対応を取ることが不可欠です。
- 隔離
カビの生えた着物を、他の衣類とは別の場所に隔離します。その際、ビニール袋などに入れて密封すると、胞子の飛散を最小限に抑えられます。 - 点検
カビのあった着物の周囲に収納されていた他の着物も、カビが発生していないか一枚ずつ丁寧に点検します。 - 換気
着物を取り出した後のタンスや押し入れは、扉を開け放って十分に換気し、内部の湿気を追い出します。可能であれば、アルコールを含ませた布で内部を拭き、よく乾燥させるとより効果的です。
要するに、カビは感染症のように広がる可能性があると認識し、発見次第、迅速な隔離と周辺環境の点検・清掃を行うことが、被害の拡大を防ぐための鍵となります。

喪服は特にカビが生えやすい?
「喪服にカビが生えてしまった」というご相談は非常に多く、喪服が特にカビやすいという印象をお持ちの方も少なくありません。これにはいくつかの理由が考えられます。
第一に、喪服は着用機会が限られており、一度着た後に長期間タンスにしまいっぱなしになることが多い点です。着用後の手入れが不十分なまま何年も保管されると、目に見えない汗や湿気がカビの発生原因となります。
第二に、喪服は黒地であるため、初期段階の「白カビ」が非常に目立ちやすく、発見されやすいという側面があります。
他の淡い色の着物では気づかないような小さなカビでも、黒地の喪服でははっきりと視認できるため、「喪服にカビが生えた」と認識されやすいのです。
これは、早期発見・早期対処につながるという点ではメリットとも捉えられます。
一方で、最近の喪服の多くには、水や汚れをはじく「ガード加工」が施されています。この加工はカビの発生をある程度抑制する効果も期待できますが、万能ではありません。
加工の効果は経年で薄れますし、湿度の高い環境に長期間置かれれば、やはりカビのリスクは高まります。
以上の点を踏まえると、喪服が他の着物と比べて素材的に特別カビやすいわけではありません。
しかし、「着用頻度の低さ」と「長期保管」という状況がカビのリスクを高め、「黒地であること」がカビの発見を容易にしている、というのが実情に近いと考えられます。
どのような着物であっても、着用後の手入れと適切な保管がカビ予防の基本であることに変わりはありません。

自分でできるカビの取り方・落とし方
着物にカビを発見した際、ご自身で何かできないかと考えるのは自然なことです。
ただし、自宅で安全に対処できるのは、発生して間もない、ごく表面的な「白カビ」に限定されると心得てください。
黄カビや黒カビ、広範囲に広がった白カビは、かえって状態を悪化させる危険があるため、専門家に任せるのが賢明です。
ここでは、限定的な状況下での応急処置の手順を解説します。
応急処置の手順
- 準備と場所の確保
作業は必ず屋外か、窓を全開にして換気を十分に行った室内で行います。床には新聞紙などを敷き、カビの胞子が室内に飛散するのを防ぎましょう。また、胞子の吸入や皮膚への付着を防ぐため、マスクと手袋は必ず着用してください。 - 着物をハンガーに掛ける
着物専用のハンガーに着物を掛け、作業しやすい状態にします。 - カビを優しく払う
乾いた柔らかい布や、毛先の柔らかい着物専用ブラシを使い、カビが生えている部分を生地の目に沿ってごく優しく払い落とします。この時、絶対に強く擦ったり叩いたりしないでください。強い力を加えると、カビの菌糸を繊維の奥に押し込んでしまったり、デリケートな生地を傷めたりする原因になります。 - 陰干しで湿気を飛ばす
カビを払い落としたら、そのまま風通しの良い日陰で半日から一日ほど陰干しし、着物内部の湿気を完全に取り除きます。直射日光は色褪せの原因となるため、必ず日陰で干してください。 - 後片付け
作業で使用した布やブラシ、マスク、手袋にはカビの胞子が付着しているため、ビニール袋に入れて密閉し、速やかに処分します。
この方法はあくまで応急処置です。目に見えるカビが取れたとしても、繊維の奥には菌が残っている可能性が高く、そのまま保管すれば再発のリスクが伴います。
処置後はできるだけ早く専門家に見てもらい、根本的なクリーニングを検討することをおすすめします。

ベンジンを使う際の注意点とは
着物のシミ抜きなどで「ベンジン」が使われることがありますが、ご家庭でカビ取りのために安易に使用することは推奨されません。
ベンジンは油性の汚れを溶かす力がありますが、カビ菌そのものを殺菌する効果は限定的であり、使用には多くのリスクが伴います。
ベンジン使用に伴うリスク
- 色落ち・変色の危険性
着物の染料は非常にデリケートです。ベンジンが染料と化学反応を起こし、色落ちや変色を引き起こす可能性があります。特に高価な着物や色柄の複雑な着物への使用は、修復不可能なダメージにつながる恐れがあります。 - 輪ジミの発生
: ベンジンの使い方が不適切だと、汚れが溶けて周囲に広がり、かえってシミが大きくなる「輪ジミ」が発生することがあります。 - 生地へのダメージ
強く擦ることで生地の表面が毛羽立ったり、風合いが損なわれたりする可能性があります。 - 引火の危険性
ベンジンは揮発性が高く、非常に引火しやすい物質です。静電気やわずかな火花でも引火する危険があるため、火の気のない、換気が十分な場所で取り扱う必要があります。
プロに任せるべき理由
データベースで参照した情報の中には、セルフケアとしてベンジンを使用する方法が示唆されているケースも見られますが、これは専門的な知識と技術を持つ職人が行うことを前提としたものです。
カビの状態や着物の素材を見極め、適切な量と方法で処置しなければ、前述のような失敗を招きかねません。
要するに、ご家庭でのベンジン使用はメリットよりもリスクの方がはるかに大きいと言えます。
カビやシミで悩んだ際は、自己判断で薬品を使おうとせず、着物の状態を正確に診断できる専門のクリーニング店や悉皆屋(しっかいや)に相談することが、最も安全で確実な方法です。

カビだらけの着物を業者に頼む場合の選択肢
ご自身での対処が難しいカビや、根本的な解決を望む場合、プロの手に委ねるのが最善の選択です。専門業者には、カビの状態や予算に応じて様々なクリーニング方法があります。
このセクションでは、業者に依頼する際の具体的な選択肢と、それぞれの料金、そしてクリーニング以外の活用法について解説します。
専門業者のクリーニング料金の目安
着物のカビを専門業者に依頼する際、料金はカビの状態や着物の種類、そして選択するクリーニング方法によって大きく異なります。
まずは基本的なクリーニングである「丸洗い」と、カビ取りに特化した「カビ取り丸洗い」の料金相場を把握しておきましょう。
「丸洗い」は、着物を解かずにそのままの形で石油系の専用溶剤で洗う、いわば着物専用のドライクリーニングです。
全体のホコリや軽い皮脂汚れを落とすのが主な目的で、残念ながらこれだけではカビ菌を完全に死滅させたり、定着したシミを落としたりすることは困難です。
そこで、カビが主なお悩みの場合は「カビ取り丸洗い」を選択する必要があります。
これは、通常の丸洗いの工程に加え、カビ取り専用の溶剤を用いたり、職人が手作業でカビを処理したり、オゾンなどで殺菌・消臭したりする特別なメニューです。
当然、料金は通常の丸洗いよりも高くなります。
以下に、一般的な料金の目安を表にまとめました。ただし、これはあくまで相場であり、お店やカビの深刻度によって変動するため、必ず事前に見積もりを取るようにしてください。
| 着物の種類 | 丸洗い(目安) | カビ取り丸洗い(目安) |
|---|---|---|
| 小紋・紬・色無地 | ¥9,000 ~ ¥12,000 | ¥20,000 ~ ¥25,000 |
| 訪問着・付下げ | ¥10,000 ~ ¥13,000 | ¥22,000 ~ ¥28,000 |
| 振袖 | ¥13,000 ~ ¥16,000 | ¥25,000 ~ ¥30,000 |
| 黒留袖(比翼付) | ¥12,000 ~ ¥15,000 | ¥28,000 ~ ¥33,000 |
| 長襦袢 | ¥5,000 ~ ¥8,000 | ¥15,000 ~ ¥20,000 |
| 袋帯・名古屋帯 | ¥8,000 ~ ¥11,000 | ¥18,000 ~ ¥23,000 |
この表から分かるように、カビ取りには相応の費用がかかります。カビの発見が遅れれば遅れるほど、より高度な技術が必要となり、料金も高くなる傾向にあります。
早期発見・早期相談が、結果的に費用を抑えることにも繋がるのです。

洗い張りなど高額になる場合の料金
黄カビや黒カビが広範囲に発生している場合や、生地の風合いを取り戻して根本から再生させたい場合には、「洗い張り(あらいはり)」という選択肢が浮上します。
これは、丸洗いとは全く異なる、伝統的な着物の洗濯方法です。
「洗い張り」とは、着物を一度すべてほどいて縫い目を解き、一枚の反物の状態に戻してから、水と専用の洗剤で丁寧に洗い上げる方法です。
これにより、繊維の奥深くに染み込んだ汚れやカビ菌、古い糊までしっかりと洗い流すことができます。
洗浄後は、生地を張り木や伸子(しんし)で伸ばしながら乾燥させることで、生地の幅を整え、縮みを補正し、本来の光沢や風合いを蘇らせます。
この方法は、カビ除去において非常に高い効果を発揮しますが、それに伴い料金も高額になります。
費用は大きく分けて「洗い張りの料金」と「再仕立ての料金」の二つで構成されることを理解しておく必要があります。
- 洗い張りの料金
反物の状態にして洗う作業自体の費用です。着物の種類にもよりますが、表地だけでおおよそ ¥11,000~¥20,000 程度が相場となります。 - 再仕立ての料金
洗い張りで反物の状態になった生地を、再び着物の形に縫い上げるための費用です。これは「お仕立て代」とも呼ばれ、洗い張りの料金とは別に発生します。袷(あわせ)の訪問着であれば ¥45,000以上、振袖となるとさらに高額になるのが一般的です。
したがって、洗い張りで着物を再生させる場合の総額は、洗い張り代+再仕立て代(+裏地交換が必要な場合はその費用)となり、小紋でも総額で6万円以上、訪問着や振袖では10万円を超えることも珍しくありません。
高額ではありますが、洗い張りは単なるクリーニングではなく「着物の再生」と言える根本的な処置です。
親から受け継いだ大切な着物など、費用をかけてでも蘇らせたい一着にとっては、最も有効な手段となり得ます。

処分・捨てる以外のリメイク・リサイクル
カビの状態が深刻でクリーニング費用が高額になる場合や、特段思い入れがなく着用予定もない場合、「処分・捨てる」という選択肢が頭をよぎるかもしれません。
しかし、その前にいくつかの活用法を検討する価値があります。
着物専門の買取業者に査定を依頼する
「カビの生えた着物なんて売れるはずがない」と思いがちですが、専門の買取業者であれば買い取ってくれる可能性があります。業者には独自の販売ルートや修復ノウハウがあるためです。
- 価値の高い着物
有名作家物や希少な染織品など、着物自体の価値が高ければ、カビによる減額を差し引いても買取価格がつくことがあります。 - 部分的な活用
カビていない部分の生地をリメイク素材として販売するルートを持っている業者もいます。 - 海外での需要
海外では日本の着物が人気であり、多少のシミやカビを気にしない文化もあるため、そうした市場向けに買い取られるケースもあります。
査定は無料で行っている業者がほとんどなので、捨てる前に一度相談してみることをお勧めします。
フリマアプリやネットオークションで売る
カビの状態を正直に、かつ詳細に説明し、写真を掲載することを前提に、フリマアプリなどで販売する方法もあります。
自分で価格を設定できるメリットがありますが、出品や梱包、発送の手間がかかる点、そして買い手とのトラブルは自己責任となる点を理解しておく必要があります。
リメイクで新たな命を吹き込む
着物としては着られなくても、その美しい生地を活かして新たな品に生まれ変わらせる「リメイク」も素晴らしい選択肢です。
- 小物へ
バッグ、ポーチ、袱紗(ふくさ)、クッションカバーなど、比較的小さな面積でも作れるものはたくさんあります。 - 洋服へ
カビのない部分が広ければ、ブラウスやスカート、ワンピースなどに仕立て直すことも可能です。
裁縫が得意な方はご自身で、苦手な方は着物リメイクを専門に行う業者に依頼することもできます。思い出の着物を形見として手元に残したい場合に、特におすすめの方法です。
これらの方法を検討することで、単にゴミとして処分するのではなく、着物の価値を最後まで活かしきることが可能になります。

今後のための正しい保管方法と手入れ法
一度カビを除去しても、保管環境や手入れの方法が以前と同じであれば、再発のリスクは常に残ります。大切な着物をカビから守り、長く美しい状態を保つためには、日頃からの適切な管理が何よりも大切です。
保管の基本は「湿気対策」と「通気性」
- 湿度管理
着物の保管に最適な湿度は40%~60%とされています。除湿機やエアコンのドライ機能、あるいはタンス用の除湿剤を活用して、湿度が高くなりすぎないように管理しましょう。除湿剤は着物に直接触れないように置き、定期的に交換することが肝心です。 - 保管場所
湿気がこもりやすい1階や北側の部屋、水回りの近くは避け、風通しの良い2階以上の部屋などが望ましいです。タンスは壁から5cmほど離して置くと、空気の通り道ができて湿気がこもりにくくなります。 - 桐たんすの活用
桐は湿度を調整する機能や、虫を寄せ付けにくい成分を含むため、着物の保管に最も適した素材とされています。お持ちでない場合は、通気性の低いプラスチックケースは避け、桐製の衣装箱などを活用するのも一つの手です。
日頃の手入れと定期的な点検
- 着用後の陰干し
着用した着物は、体温や汗、空気中の湿気を含んでいます。すぐにタンスにしまわず、必ず着物ハンガーに掛けて、風通しの良い室内で半日~1日陰干しし、湿気を完全に飛ばしてください。 - たとう紙の交換
着物を包む和紙「たとう紙」は、湿気を吸ったりホコリから守ったりする役割があります。しかし、たとう紙自体が湿気を吸いすぎると効果が薄れ、カビの原因にもなります。黄色く変色したり、シワシワになったりしたら交換のサインです。1~2年を目安に新しいものに取り替えましょう。 - 虫干し(陰干し)
年に2~3回、空気が乾燥している時期(10月~2月頃)に虫干しを行うのが理想的です。晴天が2~3日続いた日の日中に、着物をタンスから出してハンガーに掛け、室内の風通しの良い場所で数時間、風に当てます。これにより、こもった湿気を飛ばし、カビや虫の発生を予防します。時間がなければ、タンスの引き出しをすべて開け放ち、扇風機で風を送るだけでも効果があります。
これらの地道な手入れを習慣づけることが、高価なクリーニング代を節約し、お着物を末永く愛用するための最も確実な方法と言えます。

カビだらけの着物を諦める前に
この記事では、カビだらけになってしまった着物の原因から、ご自身での応急処置、専門業者によるクリーニング、そして今後のための予防法まで、幅広く解説してきました。
最後に、絶望的な状況に思えても諦める前に、ぜひ押さえておきたい重要なポイントをまとめます。