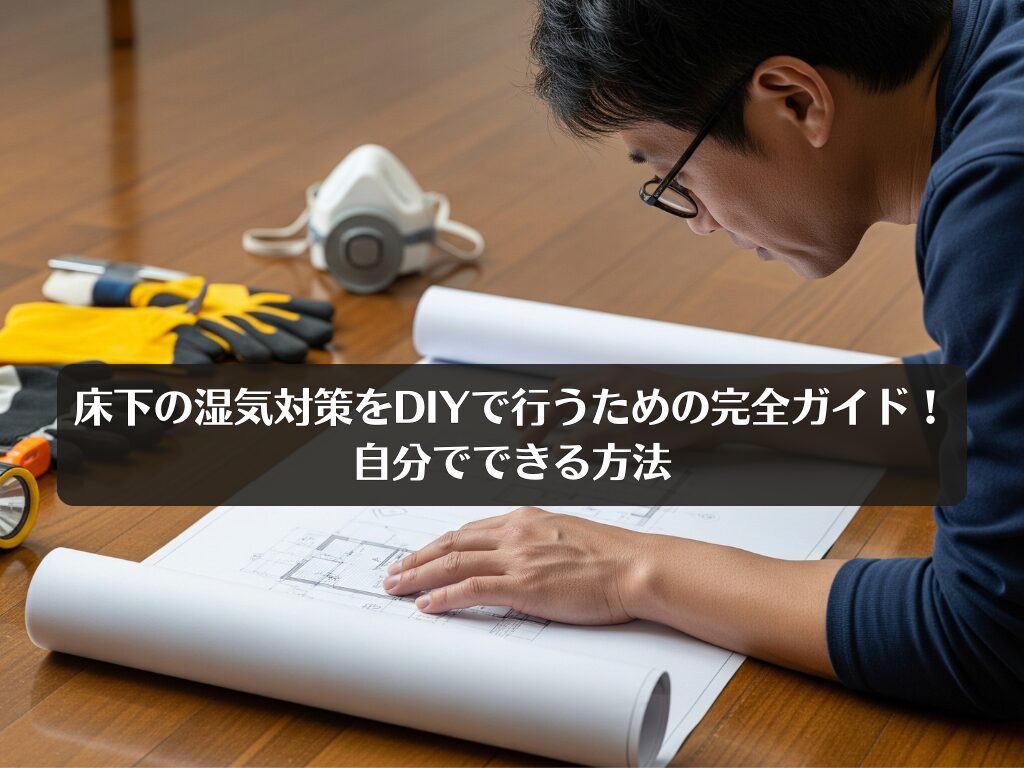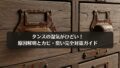カビや腐食の原因となる、ひどい床下の湿気。専門業者に頼むと費用もかかるため、床下湿気対策のDIYを自分でやってみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、ただやみくもに対策しても、失敗や後悔につながる可能性があります。
例えば、防湿シートの効果を正しく理解していなかったり、床下調湿剤のデメリットを知らずに使ってしまったりするケースです。
そもそも、ご自宅の基礎がベタ基礎やコンクリートの場合、対策は本当に必要なのでしょうか。
また、炭や石灰、ゼオライトといった材料を使い、正しい乾燥させる方法や湿気を取る方法を実践するにはどうすればよいか、疑問は尽きません。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、床下の湿気対策に関する網羅的な情報を提供します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
DIYで床下の湿気対策を始める前の基本知識
ひどい湿気?まずは状態を確認
床下の湿気対策を始めるにあたり、何よりも先に行うべきは、床下の現状を正確に把握することです。
なぜなら、湿気の度合いや原因によって、最適な対策方法が大きく異なるからです。
まず、床下点検口から内部を覗き、懐中電灯などで照らして目視で確認します。
カビ特有のツンとした臭いや土臭さが充満していないか、嗅覚も使ってチェックしましょう。
具体的には、以下の点に注意して確認作業を進めます。
- 地面の状態
地面が土の場合、表面が明らかに湿っていたり、水たまりができていたりしないか確認します。 - 木材の状態
住宅の基礎となる土台や大引といった木材が、変色したり、白い綿のようなカビや黒い斑点が付着したりしていないか観察してください。 - 配管の結露
キッチンや浴室の真下にある給排水管に水滴が付いていないかも、重要なチェックポイントです。 - 害虫の痕跡
シロアリが作った土のトンネル(蟻道)や、クモの巣、その他の不快害虫の死骸がないかも見ておきましょう。
これらのサインが見られる場合は、湿気がひどい状態にあると考えられます。
安全のため、作業時は汚れてもよい長袖長ズボン、マスク、ゴーグル、手袋を必ず着用してください。

ベタ基礎やコンクリートの床は対策不要?
ご自宅の基礎の構造を理解することは、適切な湿気対策を見極める上で非常に大切です。
特に、床下がコンクリートで覆われている「ベタ基礎」の住宅は、地面からの湿気対策が基本的に不要な場合があります。
ベタ基礎は、建物の底一面を鉄筋コンクリートで覆う工法です。このコンクリート自体が、地面から上がってくる水蒸気を遮断する防湿層の役割を果たします。
そのため、地面が土のままの「布基礎」に比べて、格段に湿気が上がりにくい構造になっています。
ただし、ベタ基礎だからといって、全く安心というわけではありません。注意すべき点がいくつかあります。
第一に、建物の周囲の風通しが悪く、床下の換気が十分に行われていないケースです。基礎に設けられた換気口が物置や雑草で塞がれていると、空気がよどみ、湿気がこもりやすくなります。
第二に、配管からの水漏れや、台風などの集中豪雨で床下に水が浸入した場合です。一度入り込んだ水がうまく排出されないと、コンクリートの上で湿気が滞留し、カビの原因となる可能性があります。
したがって、ベタ基礎やコンクリート床の住宅であっても、換気口の状態や水漏れの有無など、定期的な点検を怠らないことが肝心です。

自分でできる代表的な方法
床下の状態を確認し、対策が必要だと判断した場合、自分でできるDIYにはいくつかの代表的な方法があります。
これらは専門的な技術を必要とせず、ホームセンターなどで材料を揃えられるため、多くの方が挑戦しやすいと考えられます。
主な方法は以下の通りです。
- 換気口の清掃と確保
最も手軽で基本的な対策です。家の基礎にある換気口の前に置かれた物や生い茂った雑草を取り除き、空気の通り道を確保します。 - 防湿シートの敷設
地面が土の場合に非常に効果的です。地面を物理的に覆うことで、土壌からの水蒸気の上昇を根本から遮断します。 - 床下調湿剤の設置
湿気を吸ったり吐いたりして湿度を調整する材料を床下に置きます。炭、ゼオライト、シリカゲルなどが代表的です。 - 石灰の散布
古くから行われている方法で、消石灰を撒くことで湿気を吸収させると同時に、カビの発生を抑制する効果が期待できます。 - 床下換気扇の設置
強制的に床下の空気を入れ替え、湿気を排出する方法です。ただし、これには電気配線が伴うため、DIYとしては難易度が高くなります。
これらの対策は、一つだけ行うのではなく、例えば防湿シートを敷いた上で調湿剤を置くなど、複数を組み合わせることで、より高い効果を発揮します。

床下を乾燥させる方法
本格的な湿気対策を施す前に、床下をできる限り乾燥させることが、対策効果を最大化する上で鍵となります。
湿った状態で防湿シートを敷いたり調湿剤を置いたりしても、閉じ込められた湿気が原因で、かえって状況を悪化させる可能性があるためです。
床下を乾燥させる方法は、主に換気の促進です。
まずは、家の基礎に設けられている換気口の周りを徹底的に片付け、空気の流れを妨げている障害物を全て取り除きます。
エアコンの室外機や物置、植木鉢、伸び放題の雑草などが原因で、空気の通り道が塞がれていないかを確認してください。
風通しを良くした状態で、晴れた日が続くのを待ち、自然の力で床下を乾燥させます。
数日間、送風機やサーキュレーターを床下点検口から内部に向けて作動させ、空気の流れを強制的に作り出すのも有効な手段です。
このとき、対角線上にある換気口に向けて風を送ると、床下全体の空気が効率的に循環しやすくなります。
床下の土がひどく湿っている場合は、この乾燥工程に十分な時間をかけることが大切です。土の表面が乾いて見える状態になるまで、根気よく換気を続けましょう。

実際にかかる費用は?
床下の湿気対策をDIYで行う最大のメリットの一つは、専門業者に依頼するよりも費用を大幅に抑えられる点です。
具体的な金額は、選択する対策方法や住宅の広さによって変動しますが、おおよその目安を知っておくと計画を立てやすくなります。
| 対策方法 | 主な材料 | 費用目安(一般的な30坪住宅の場合) |
|---|---|---|
| 換気口の清掃 | ブラシ、掃除用具など | ほぼ0円 |
| 防湿シート敷設 | 防湿シート、防湿テープ | 5,000円~20,000円程度 |
| 床下調湿剤設置 | ゼオライト、炭、シリカゲルなど | 10,000円~50,000円程度 |
| 石灰散布 | 消石灰 | 5,000円~15,000円程度 |
防湿シートは、メーター単位で購入できる場合もあり、必要な分だけ無駄なく購入することで費用を抑えられます。
床下調湿剤は、製品や種類によって価格に幅がありますが、比較的安価なゼオライトやシリカゲルを選ぶとコストを削減可能です。
これらの材料費に加えて、マスクや手袋、ゴーグルといった安全装備の購入費用も考慮に入れておくとよいでしょう。
複数の対策を組み合わせる場合は、それぞれの費用を合算して全体の予算を算出します。
いずれにしても、業者に依頼した場合の数十万円という費用と比較すると、DIYは非常に経済的な選択肢と言えます。

素材別!床下の湿気対策DIYの実践ガイド
防湿シートの効果
地面が露出している布基礎の住宅において、防湿シートの敷設は最も効果的な湿気対策の一つです。
その最大の効果は、地面から揮発してくる水蒸気を物理的にシャットアウトし、床下空間の湿度上昇を根本から抑制することにあります。
シートは厚さ0.1mm以上のポリエチレン製フィルムが一般的で、これを床下全面に隙間なく敷き詰めることで効果を発揮します。
正しい敷設の手順
- 床下の清掃と乾燥
前述の通り、シートを敷く前に床下のゴミを取り除き、土を十分に乾燥させてください。 - シートの敷設
床下全面を覆うようにシートを広げます。このとき、シート同士の重ね合わせ部分は、最低でも15cm以上確保することが重要です。この重ね幅が不十分だと、隙間から湿気が漏れ出してしまい、効果が半減します。 - 重ね部分の固定
重ねた部分は、湿気に強い布テープや専用の防湿テープでしっかりと貼り合わせ、密閉します。 - 端の処理
シートの端は、基礎の壁に沿って少し立ち上げるようにして敷くと、壁際からの湿気の回り込みを防ぐのに役立ちます。 - 重しを置く
敷設したシートがずれないように、上に砂利や砂を薄く撒いたり、重しとして炭袋などを置いたりするのも有効な方法です。
この作業を丁寧に行うことで、地面からの湿気という最大要因を断ち切ることができ、床下環境を劇的に改善できる可能性があります。

石灰の散布
古くから日本の住宅で用いられてきた湿気を取る方法として、石灰の散布が挙げられます。DIYで用いるのは、刺激が比較的穏やかで安全性の高い「消石灰」です。
石灰を撒くことには、二つの大きなメリットがあります。
- 吸湿性
消石灰自体が持つ吸湿性により、床下の湿気を吸収してくれることです。 - 殺菌効果
石灰が持つ強アルカリ性の性質により、カビや雑菌の繁殖を抑制する効果が期待できます。
散布の手順と注意点
散布する際の目安量は、1平方メートルあたり約1kgです。床下全体に均一になるように、スコップなどを使って丁寧に撒いていきます。
ただし、石灰の取り扱いには十分な注意が必要です。消石灰は皮膚や目、呼吸器に刺激を与えるため、作業時には防塵マスク、保護ゴーグル、ゴム手袋、長袖長ズボンを必ず着用してください。
床下という閉鎖空間で作業するため、粉塵を吸い込まないよう特に注意が求められます。
また、散布直後は床下の換気を十分に行い、舞い上がった粉が室内に侵入しないように配慮することも大切です。
安全管理を徹底すれば、低コストで湿気とカビの両方に対策できる有効な手段です。

半永久的に使える炭の設置ポイント
床下調湿剤として人気の高い素材の一つが炭です。
炭が持つ無数の微細な孔(あな)が、湿気が多いときには水分を吸着し、逆に空気が乾燥しているときには水分を放出する「調湿効果」を発揮します。
この吸放湿機能は劣化しにくいことから、一度設置すれば半永久的に効果が持続すると紹介されることが多いのですが、実際には常時高湿度の床下環境では短期間で飽和し、孔の目詰まりなどで性能が低下する場合があります。
そのため、2~3年ごとに取り出して天日干しで乾燥させるか、状態を点検して必要に応じて追加・交換を行うことで、調湿性能を長持ちさせることができます。
さらに、炭には湿気対策だけでなく、カビ臭などの嫌な臭いを吸着する消臭効果や、シロアリなどの害虫を寄せ付けにくくする防虫効果も期待できます。
効果的な設置のポイント
炭を設置する際は、不織布などの通気性の良い袋に入った製品を選ぶと、床下での取り扱いや配置が容易になります。
設置量は製品によって異なりますが、1坪(約3.3平方メートル)あたり2~4袋程度が一般的です。
設置の鍵は、床下全体に均等に配置することです。
空気のよどみやすい部屋の隅や、湿気が特に気になる場所に重点的に置きつつも、一箇所に集中させず、間隔をあけて満遍なく並べていくことで、床下全体の湿度を効率的にコントロールできます。
前述の通り、防湿シートを敷いた上に炭を置くと、地面からの直接的な水分吸収を防ぎ、空気中の湿度調整という本来の役割に集中させることができるため、より高い効果が期待できるでしょう。

市販のゼオライトを効果的に使うには?
ゼオライトも、炭と並んで代表的な床下調湿剤の素材です。
これは火山活動によって生まれた天然の鉱物で、炭と同様に微細な孔を持つ多孔質構造をしています。
そのため、優れた調湿効果を発揮し、床下の湿度を安定させるのに役立ちます。
ゼオライトの多くは砂利状になっており、袋から出して床下に直接撒いて使用するタイプが主流です。
この形状は、狭い床下でも扱いやすく、均一に敷き詰めやすいというメリットがあります。
ゼオライトを効果的に使うための注意点
ゼオライトを使用する際も、まず防湿シートを敷設した上に撒くのが最も効果的です。
湿った土の上に直接撒いてしまうと、ゼオライトが土の水分を吸い続けて飽和状態になり、空気中の湿度を調整する能力が早期に失われてしまう可能性があります。
製品に記載されている1坪あたりの推奨使用量を守り、厚さが均一になるように丁寧に撒き広げてください。
アイリスオーヤマの「床下さらり」など、市販されている製品には、調湿効果に加えて防カビや防虫、消臭効果が付加されているものも多く、これらを選ぶことで一つの製品で多角的な対策が可能になります。
比較的安価で入手しやすいため、コストを抑えたい場合の有力な選択肢です。

床下調湿剤のデメリットと注意点
床下調湿剤は手軽で効果的なアイテムですが、その使用にあたってはいくつかのデメリットや注意点を理解しておくことが不可欠です。
これを知らずに設置すると、期待した効果が得られないばかりか、かえって問題を悪化させることにもなりかねません。
最大の注意点は、調湿剤の吸湿能力には限界があるという点です。調湿剤は、湿気を吸収しきって飽和状態に達すると、それ以上は吸湿できなくなります。
さらに悪いことに、周囲の環境変化によっては、一度吸収した湿気を再び放出してしまうことがあります。
例えば、地面からの湿気が非常に多い場所に防湿シートなしで調湿剤を直接撒いた場合、調湿剤はすぐに水分でいっぱいになり、本来の調湿機能を果たせなくなります。
また、換気が不十分で湿気が常に供給され続けるような環境では、調湿剤をいくら置いても根本的な解決にはなりません。
調湿剤を過剰に置きすぎるのも逆効果となる場合があります。飽和した調湿剤が床下全体の湿度を逆に高めてしまい、カビやシロアリの発生を助長するケースも報告されています。
これらのことから、床下調湿剤は、換気の確保や防湿シートの敷設といった根本的な対策と組み合わせて使用する補助的な手段と捉えるのが賢明です。
製品ごとに定められた適切な量を守り、定期的に床下の状態を点検することが求められます。
より専門的な見地から床下環境について知りたい、あるいは湿気とシロアリ被害との関連性を深く理解したい場合は、以下の専門機関の情報が非常に参考になります。
住宅の天敵であるシロアリの防除に関する調査研究や広報活動を行っている公益社団法人 日本しろあり対策協会。
ウェブサイトでは、シロアリの生態だけでなく、その発生要因となる床下の湿気環境の重要性についても詳しく解説されています。

DIYで行う最適な床下湿気対策とは?
これまで解説してきたように、床下の湿気対策DIYには様々な方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
最適な対策は、ご自宅の基礎の構造、湿気の原因と度合い、そしてかけられる予算や手間によって異なります。
これらを総合的に判断し、ご自身の状況に最も合った方法、あるいは複数の方法の組み合わせを選択することが、成功への道筋となります。
以下に、これまでの重要なポイントをまとめます。